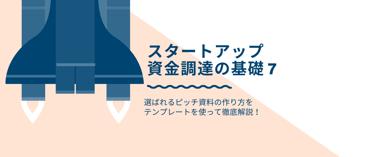2013年に政府が閣議決定した「日本再興戦略」内で「健康経営」が重要なテーマとして挙げられたのを皮切りに、2015年にはストレスチェックの義務化や、経済産業省と東京証券取引所の共同施策「健康経営銘柄」の選定が始まるなど、従業員の健康管理への関心は益々高まりを見せている。従業員の活力向上が組織全体の生産性向上に繋がり、企業の中長期的な業績の向上の実現に繋がることが期待されているのである。
一方で、現場の人事・総務担当、あるいは経営者は「健康経営に向けて、具体的に何から取り組んだらいいのか?」について日々、頭を悩ませている。そんな法人向けに企業の健康管理業務をオールインワンで提供しているのが株式会社iCAREだ。代表の山田氏は、起業家でもありながら元々は離島医療の現場で働いていた現役産業医だ。今回は、日本でまだ健康経営に対する意識が高まり切っていなかった2011年に会社を設立させた山田氏と、同社に2015年に投資を行ったインキュベイトファンドの和田に対して、「働くひとと組織の健康」に対する思いとこれまでの歩みに迫る。
既存の経済・社会の仕組みやルールでは達成できない「インパクト」を創出すべく、スタートアップとして課題に取り組む未来を創る挑戦者と、彼らと一緒に取り組むベンチャーキャピタリストの対談シリーズ「8 answers」。起業家が社会に残そうとしている世界観や、それに対する彼らの情熱をお伝えする。
-png.png)
プロフィール
山田 洋太(やまだ・ようた)
株式会社iCARE 代表取締役CEO
金沢大学医学部医学科卒業後、2005年沖縄県立中部病院研修。
2008年離島医療(久米島)に従事。2012年3月、慶應義塾大学大学院経営管理研究科(MBA)修了。大学院と並行して心療内科を学び、すでに2万名以上メンタル不調者と関わる。病院再建では経営企画室室長として経営黒字化を先導。厚生労働省が行う検討会にて産業医の立場から提言。同省「VDT検診見直し検討会」の委員も務める。
和田 圭祐(わだ・けいすけ)
インキュベイトファンド株式会社 General Partner
2004年フューチャーベンチャーキャピタル入社、ベンチャー投資やM&A アドバイザリー業務、二人組合の組成管理業務に従事。
2006年サイバーエージェントへ入社し、国内ベンチャー投資、海外投資ファンド組成業務、海外投資業務に従事。
2007年シード期に特化したベンチャーキャピタル、セレネベンチャーパートナーズを独立開業。
2010年にインキュベイトファンド設立、代表パートナー就任。
病気になってからでは遅い。医師として患者の”本当の意味での健康”を追求し、辿り着いた「起業」という選択肢

――まず最初に自己紹介をお願いします。
山田:株式会社iCAREのCEO、山田と申します。iCAREは、2011年に創業した法人向けのヘルスケアサービスを提供している会社です。人事や総務といったバックオフィス向けのサービスとして、従業員の健康管理にまつわる課題をクラウドで解消するクラウドシステム「Carely」を提供しています。Carelyは5年前にローンチしているのですが、つい先日、Carely上で管理している健康データの分析から課題抽出・改善策の実施までを行うことができる健康経営プラットフォーム「Carely Place」をローンチしました。よろしくお願いします。
和田:インキュベイトファンド和田です。シード投資に特化したベンチャーキャピタルとして、創業直後の会社にベンチャー投資を行っています。山田さんに投資したのは、確か2015年ですかね。
山田:そうですね。
和田:本日は投資前後から現在に至るまでの山田さんとの歩みをお話できればと思ってます。インキュベイトファンドは、会社の設立前、あるいは創立して間もないタイミングから相談を受けることが多いファンドなんですが、iCAREの場合は創業が2011年なので、割と社歴がある状況で投資をさせていただいてますね。
――よろしくお願いします。山田さんは元々は医師だったとのことですが、起業に至るまでの経緯について教えていただけますか。
山田:そうですね。もともとは、僕、総合内科医という専門の医師でして。高血圧や心筋梗塞になったあとの患者さんの診療や再発予防を主に担当しておりました。内科医をやっているとうつ病や不眠症の方を診させていただくことも多いのですが、彼らに向き合っていると、彼らの近くに産業医がいるということに気づくんですね。その産業医の先生と話していると、まぁ、これがいろんな先生がいらっしゃるのだなと。本当に素晴らしいと思えた先生もいたのですが、失礼ながらそこまで素晴らしいと思えなかった方もいらっしゃいました。
その様子を見ていた時に、病気になってから産業医や医師に頼るのでは限界があり、それ以前の予防をやっていかないとという気持ちが強くなったんです。病気になってから治療しようとすると、内服やカウンセリングといった治療の手段がありますが、やはりできればお薬は使いたくないという方が多いですし、カウンセリングは時間がかかります。もっともっと未然に防いでいかないと、本当の健康は作れないんじゃないのと思っていまして。
そこで産業医の資格をとって、いろんな企業様で産業医をやらせてもらいました。ただ、企業の健康管理という観点では、明らかに産業医だけでは解決しえない問題が山積みなんですよ。産業医だけでは解決出来ない健康管理の問題を、自分だけではなくてテクノロジーの力と賛同してくれる仲間と一緒に、解決に持っていきたい。社会に対して根本的に健康管理の問題を解決するのはこの方法がベストなんじゃないかというのが、起業した一番最初の経緯です。
複雑で煩雑な「健康管理」業務を、テクノロジーとコンサルテーションの力で支援する

――産業医として企業で働いたこともある山田さんからみた、日本の企業の健康管理の現状や課題感についてお伺いしたいです。
山田:高度成長期に経済がどんどん伸びてきた中で、「診療所みたいなものを会社に作って、そこで健康管理しようよ」という発想から出てきたのが、現在の産業医を中心とした健康管理の仕組みです。それはそれでいいことなんですが、一方で、例えば過重労働など、そもそも働く環境が悪いのにその環境に対する改善が進まず、その結果従業員がどんどん健康を害していくということが起きています。法律でたくさん明記されてはいるものの、結構複雑なので、なかなか人事の方がモチベーション高く「働き方と従業員の健康を改善したい」ということが起こらなかったんですよね。なので、我々は企業向けにそういった煩雑な健康管理業務を、改善出来るサービスを提供することで、その空いた時間で人事・労務の方々が健康施策を実行出来るようになり、より健康な組織、そして健康に働く個人を創れるような社会にしていきたいと考えています。
――人事・労務の方にとって、健康管理業務が煩雑すぎると。
山田:そうですね。
先ほども言ったように、そもそも働く個人の環境が「健康になれる環境」じゃないといけないわけですよ。健康に働けるルールであったり、そういった健全な土台をまずは作らないといけない。そのためには、もちろんテクノロジーも必要ですけど、テクノロジー以外にも知識の共有などを通して、その仕組みを作っていくところまでしっかりコンサルテーションしていくことは非常に重要かなと思っていますね。
ただ、それだけでは健康って作れないんです。そういったテクノロジーを使って各企業の健康のデータを取り、「この部門は健康リスクが高いよね」と問題のある部署の可視化ができたり、その課題を解決するためのサービスが何で、それをどうマッチングさせていくかというところが次の段階としては重要じゃないかなと思っています。予防医療のインフラのようなイメージですね。例えば、我々が提供しているサービスでストレスチェックをやると、不眠症の多い部門はここですっていうのが一目瞭然なんですね。それが分かったからと言って、人事の方からするとどうしていいかわからない。知識がなかったりとか、時間がなくて対応できないっていうことが多いんですけど…iCAREさん何とかできないの?っていうご相談があるわけです。そういったときに、我々と提携している企業の研修であったり、アプリを活用して、課題が可視化された部門に対して具体的な改善策を実行していくことで、働く個人や集団、組織が健康になるというところを目指しています。
ーーありがとうございます。ここ数年で企業からの関心も高まっていそうですね。
山田:そうですね。それこそ、僕が和田さんと出会う前後の時の話なんですが、僕が営業に行った先の人事部長が、僕のプレゼンで寝たことがありまして(笑)。僕のプレゼンが下手だっていうのももちろんあるんですけども。それほど興味を持たれなかったんですよね。まあ総論は同意していただけて、「働く人の健康って大事だ」って言うと、「うん大事だ」ってなるんですけど、じゃあそこにお金を払ってまで解決したいかというと、当時はそこまでいかない会社が多かったなと。5年前、6年前と比べると、明らかに働く人の健康に注意を向けないとその会社自体の成長に影響する、というような追い風、社会の変化を肌で感じますね。
ーー和田さんも、もともとこの領域には関心があったんですか。
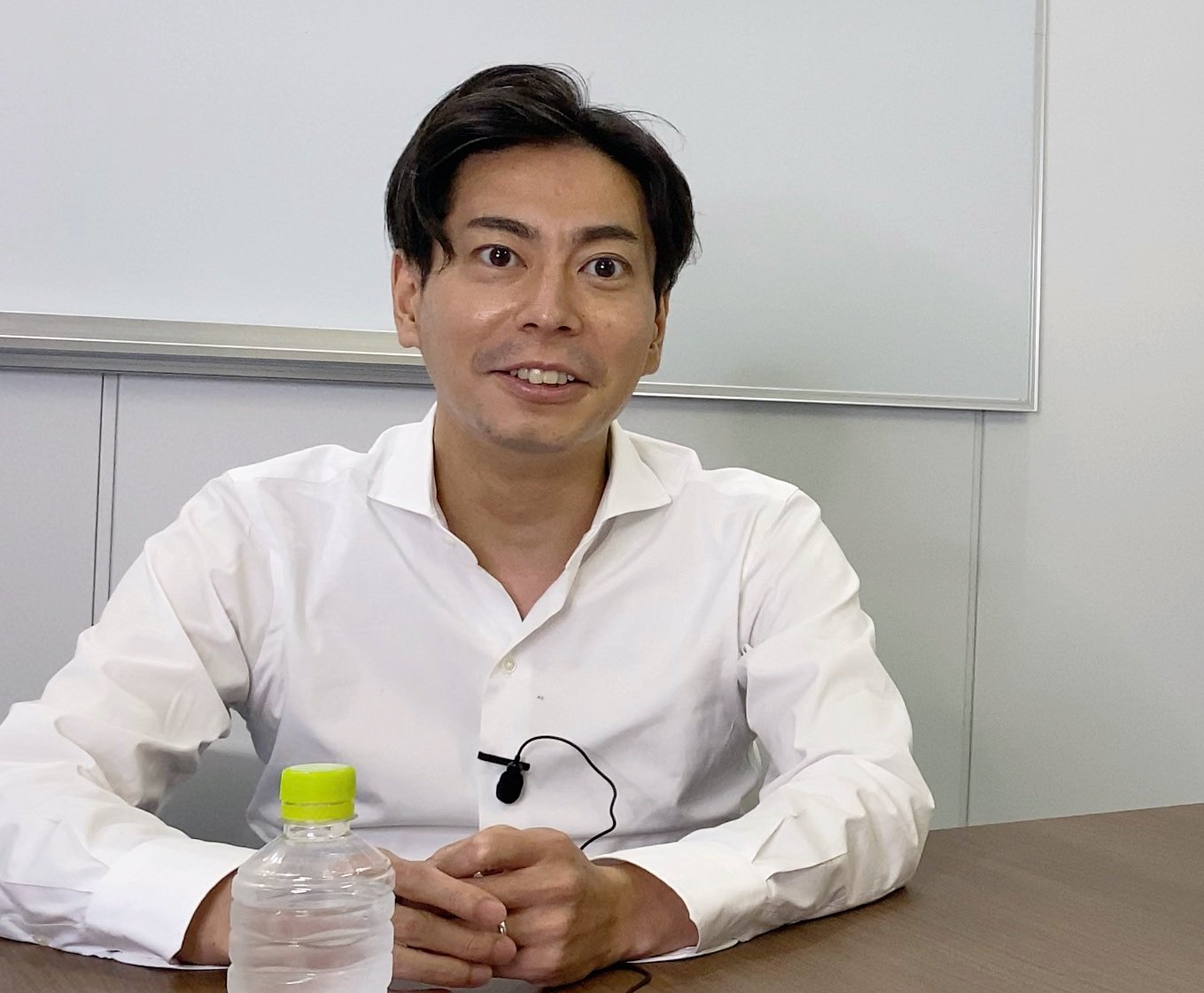
和田:そうですね。投資先はシード期から事業を作っていくスタートアップばかりなんですが、死ぬほど働くハードワークなカルチャーが、今はだいぶ改善された気がするんですけど、昔はけっこうひどくて。少数制でやってる10人の内、1人が体調を崩すとダメージがめちゃくちゃ大きくて、従業員大事にしなきゃって気持ちがある経営者もいっぱいいる中で、じゃあどう大事にすれば良いかっていうところで、なんかあんまりやりようがないと。そういったところで、病気になってから治療するのではなく、手前で病気にならないようなケアを会社からサービスとして提供するというのはあるといいなと思ってました。
そんな形で、やりたいことはふわっとあった状態だったのですが、2人の起業家の方から「iCAREの山田さんがいいんじゃないか」って言われて会って。初対面の場で、山田さん覚えてるかどうか分からないですけど、当時一緒に働いてたアソシエイトの子と2人で行って、そのアソシエイトの子が、体調不良でいきなりすごい汗が出て途中で帰ったんですよ。
山田:あー、覚えてる。
和田:「いやいや」と思って。即「病院行ってね」って言ったけど、「大丈夫か」みたいな。すげー不安で、気になってしょうがない。
山田:あー、思い出した。
和田:仕込みとかじゃなくて、「若くてめちゃめちゃがむしゃらにやってると、健康崩すこともあるよね」「本人もどういう気を付け方したら良いか分からないもんね」って話してたら、その場で、そういうこと起っちゃって。こういうことをなくすためにも、うん、そういうのもっと作らなきゃいけないっすねって。
山田:そうだった思い出した。冷や汗たらたらで。「大丈夫っす」って言ってたけど、絶対大丈夫じゃなさそうだから、途中で病院行ってもらったんでしたね。
「職人」から「経営」を経験して感じた病院経営の限界
――そういった課題がある中で、とはいえ「医師から起業家」って結構リスクですし、今までのキャリアと全然違うところをやるとなるので、本当に、よし起業しようってなったきっかけはあったんですか。
山田:僕、久米島っていう離島で島医者やってたときに、病院が経営破綻するんですよ。そのときに、僕らが職人としてすごい頑張って離島医療やってたのにも関わらず、なんで病院側が経営破綻するのかわかんなくて。で、たまたま手に取った本がMBAの経営管理の本だったんですよ。それで、地方の医療をどう持続させるかというテーマでビジネススクールに入りました。
ビジネススクールに入ってみたら、それまで医師とか看護師とかしか接してない僕が、様々な優秀なビジネスパーソンに出会うわけですよ。「あっこれだ」と。そもそも病院が経営破綻する場所、特に地方は、そもそもそこに優秀な人材がいないからだっていうことに気づくんですね。根底には「へき地とか離島医療とか、地方の医療をどう継続するかっていう経営的な観点から何とかしたい」という思い。なので、病院を卒業したタイミングで病院の経営ってのもやるんですよ、再建ですね。
でも、病院の経営って、僕がやってたのは経営企画室の室長ってポジションだったんですけど、毎日CTの件数をチェックするんですよ。月次で内科の部長の先生に「CTの件数が43件ですね、これ先月から5件下がってるんですけどどうやって上げられますか」みたいな。病院の経営上、やはり検査をまわすということが必要ではあるんですよね。でもなんかおかしいわけですよ。僕は離島医療をやってきてなるべくCTをつかわない医療をやってきたので、そこでの乖離が僕の中ですごいジレンマになって、病院で本当に健康を作りたいのかっていうことがちょっと違和感に感じてくるわけですよね。不幸な方々の状態を治していくことが、病院の経営としては必要になりますので、その不幸な状態がなくなっちゃうと経営が成り立たなくなるんですよ。
そう考えると、もちろん高い倫理観でやってる病院もいっぱいありますけど、病院が「予防」という領域に手を出すかって考えるとちょっと怪しい。そうすると、予防の領域で健康をつくるっていうのは、やはり病院とか医療を捨てた人じゃないと恐らくできないっていうのがあるので、そういったことがきっかけで起業しているというのはあります。で、その時に、ビジネススクールの同期だった人と起業しています。
銀行残高13万円からの起死回生。個人の「ギフト」が花咲く会社へ
――ありがとうございます。実際に事業を始めて、起業家としてお客さまと対峙している中で嬉しいと感じた瞬間、あるいは大変だった瞬間はどんなときですか?
山田:そうですね。創業期の話なんですが、2011年に創業してから2年くらいは病院の再建に時間がとられていたんです。起業と再建、半分半分くらいでやってたんですけど、やっぱ中途半端なんですよ。で、病院の経営再建が無事成功したんで、2013年ぐらいからですかね、iCAREで本格的にサービス活動や営業活動をやり始めたのは。
ところが、当時お金もないし、エンジニアもいないし、本当に貧弱なサービスで、このサービスが6カ月間で1社しか売れないんですよ。6カ月間で1社。赤坂の交差点の前で、共同創業者と何も進捗してないねって話をしたときに、心が折れ始めるんですよ。で、そこから不眠症です、僕が。でも気づかないんですよ。僕はストレスが専門だったんですけど、それでも気づかないっていう。でも、何か体調悪いんですよ。朝起きたらだるいし、会社行きたくないんですよね。そこで、「なんだこれ」って、自分がメンタル不調だってことに気づくんですよ。
頑張ってるけど前に進んでない状態が、起業家にとって辛いんですよ。めちゃくちゃ辛い。その後、和田さんが一緒にディスカッションをしてくれた結果、ピポットを果たすんですけど、その手前まで、そのサービスに固執していました。そのサービスを信じてたんで。そういったところで、苦しい思いは結構しましたね、それこそ3回くらいはキャッシュアウトしかけていて、「銀行に残高13万円しかない」とか結構あって。今はもうないんですが、ビルの2階にスターバックスがあるんです。そこで共同創業ともうやめようかって、もうお金ないからって、何回も話したことがありますね。
ーー何回かキャッシュアウトしそうになりながらも、何とか続けていく中で、和田さんと出会ったということですね。iCAREをやっていて、やりがいのある瞬間や、嬉しい瞬間というのはどんな時ですか?
山田:今まで無かったものが新しく生まれて、それが社会的なムーブメントに変わっていく瞬間はやりがいを感じます。例えば、先日リリースした「Carely Place」は仮説検証を繰り返して5年越しに発表したプロダクトになるので、感慨深さがありました。

Carelyを使った結果、弊社の営業担当者にフィードバックがくるわけですよ。1人で人事労務をやっている担当者から、「不安だったがCarelyに伴走いただいて、非常に高いクオリティで健康管理を推進できている」「従業員からこんな嬉しい声が出てきている」と、様々な声が寄せられていく。我々が行動したことによって、現場にあった負が解消されていくというところに非常に嬉しさを感じます。
後は、僕の人間的な価値観として、人それぞれが活躍できる場所や時間、生まれながらのギフトを持っていると思っているんですね。そのギフトが開花するような瞬間を、個人が成長することを通して実現させるのが最大の喜びです。例えば、社内でいうと中野(※編集注:取締役 CRO 中野雄介氏)。正社員第1号で入った23,4歳の若者が、こうやって5年越しに会社の経営まで携わり、10人以上のチームを纏めて、彼なりのキャリアや幸せを実現出来ている。そのこと自体がやりがいです。従業員がほんのわずかな時間でもiCAREに在籍した結果、例え他の会社に行ったとしても「やっぱりiCAREで働いて良かったよね」とか、そういう風に思えるような場を提供したいと思います。それぞれの良さがあって、その良さが花咲くということこそ、最大限に嬉しいです。
一貫した行動が自分の応援者を作り出す
――ちなみに、和田さんと出会ったとき、お互い印象というのは?

山田:僕、当時、VCという存在をあまり知らなくて、基本的に疑いの目なんですよ。「怪しいやつ来た」って。確かに怪しいんですよ。でも、当時投資家の方と会った中で、和田さんだけが自分で仮説をもってきて、「これどう?」って。ヘルスケア領域とスタートアップとしてのビジネスモデルっていうのを組み合わせて持ってきてもらったんですね。他の投資家の方々は、大変申し訳ないんですけど、勉強してないと感じることが多かったです。
2015年の5月か6月くらいに、和田さんとは数回会っていただいたんですけど、僕らも踏ん切りつかなくて、1回ちょっとステイしましょうって流れたんですよ。その後、8月か9月くらいでしたっけ?改めて和田さんからアプローチしていただいて、改めて僕らも和田さんをフラットな目で見せていただたいて。あと、和田さんの出資先の会社の方と1回会食しませんかっていうことで、胡散臭くないよってことをアピールされたんです。
和田:胡散臭いかもしれないけど、他に投資している起業家に会ってもらって、どんな雰囲気でやってるかとか伝えましたね。1回流れて止まったときも、踏ん切りがついてないだけだなっていうのは分かったので、1回ペンディングしましょうってなっても全然止まったと思っていなくて。「あっこれよくあるやつだな」と。「迷い始めたな」と。でも、どうせ絶対やることになるから、速攻連絡入れて…。山田さんがずっと長いこと自分でやってて、「VCに対してこういう風に見えてる」みたいのを聞いてたから、まあ当然1回くらい揺り戻しとか気持ち固まるまであるかなと思っていて、案の定あったくらいにしか思っていなかった。
ーー和田さんから何度かアプローチした、連絡したというのは、それほど「山田さんすごくいいな」って思っていた?
山田:それ思ってないって言えないでしょ(笑)。でも、僕も聞いていいですか?なんであの時、踏ん切りついてない山田に投資を決めれたんですか?だって踏ん切りついてないじゃないですか。明らかに。しかも胡散臭いとか思ってるわけだし。
和田:まず、世の中的に医療全体が進化していくべきで、新しい治療技術や病院経営の進化といったことは必要だと思ってますが、その中でも「会社で働く人」ってテーマの中で誰が起業家として可能性があるかって考えたときに、僕も限られた付き合いの中ではありますが、山田さんが一番ずば抜けたコミットメント、情熱があったと思います。そこまでの人は探しても絶対いないんじゃないかと。僕自身もこのテーマは必ず来るだろうって思いこんで、色々調べて是非チャレンジしたいなと思ってて。該当パーソンが誰かっていうと山田さんだろうっていう発想で、勝手に、「これ絶対僕とやることになると思った」っていう感じですかね。
あと、山田さんの起業家としての数年の苦労や、それ以前に医師として今までやってきたことが、診療から病院経営になったり、ビジネススクールって変化はしているんですけど、なんか一貫している軸みたいのは見えたんで。あとは、VCと会ってうまく話しが出来なくて、傷ついてたり、「本当に和田とやっていいのか」って立ち止まったり、この辺一個一個すげー真面目に考える人だなっていう山田さんの性格が見えたんで。
山田:センシティブ(笑)。
和田:やりたい形、世の中に必要とされるサービスになったら、一生懸命会社も作るだろうし、お客さんにも一生懸命サービス提供、頑張るじゃないかなと思えて。なんで、そこは、迷いなく。
山田:そうっすね、あの当時も思い出しても明らかに迷いがないんですよ。迷ってんのは僕だけみたいな。なるほどね、ありがとうございます。
和田:当時、健康経営とか働き方改革っていう言葉もなかったですよね。ストレスチェックも始まってなかった。
山田:始まってないです。法整備ができそうか、できないか、みたいな。全然、スタートしてないんですよ。
ーー実際に投資を受けようってなって、そのあとは結構な頻度で?
山田:うん、週一で。本当に毎週やるんですよ。毎週やることの意義ってすごい高いなって思っていて、例えばその人が起業家で事業の経験しているのであれば別にいらない可能性もありますが、僕みたいに職人あがりで何も経験してない人にとって、週一で方向性が確認されたりとか、もしくはさっきも言ったんですけど売れずに、ずっと0って報告するときも多々あるわけじゃないですか。そういった中でも、「いや大丈夫だ」「このままいけば必ず売れるから」とか、「ここの部分ちょっとチューンアップした方が良いよ」とか、背中を押すという役割を含めてそういった形で週一でやっていただくことのメリットって極めて高いんですよ。
一方で、少し、まあ手を抜いてしまっているんだろうな…っていうとき、明らかに和田さん分かっているんですよ。その時は表情が変わるんで、僕らも、「申し訳ないです」みたいな感じ。目指すべき目標っていうのがあるので、そこに向けて気を抜かずにぐっと走り切らなきゃいけないわけじゃないですか。そう思っていくと、やっぱ伴走者っていうのはすごい大事な役割を果たすと思うんですね。最初にローンチしてから、1,2年は、そんなに売れているわけではないし、申し訳ない気持ちの方が強いわけですよ。これだけ出資していただいて、お金は揃った、メンバーも揃った、でもプロダクトがなかなか売れない。価値がなかなか出せてない、みたいな。そういった時期でもこういった形で伴走してもらったというのは本当にありがたいですよね。本当にありがたい。
ーー山田さんの魅力を伝える記事にしたいと思ったんですけど、すごく良いこと言っていただいて。ありがとうございます。
プロダクト、そして経営を通して関係者全員を幸せに
――お互いの一言で印象的だったものがあれば教えてください。
山田:さっきの重複にはなりますが、中途半端な気持ちで事業やっていたときに怒られたっていうところは覚えています(笑)。
和田:まったく覚えてない…。
山田:ローンチしてから1,2年経った頃でしょうか。詳細はあんまり覚えていないんですけど、確かにちょっと手を抜いていたんですよ。それで、飄々とした感じで会議にのぞんだ時があって。そしたら「これいけてなくないですか」みたいなのことを言われたことを覚えております。
あとは、僕の起業家、CEOとしての未熟さの部分ですが、売り上げ100億円を達成したいという気持ちは当然ありますし、それを叶えていくことは世の中にとっても良いことだと思っていますので、必ず実現するんですけど。じゃあそのタイミングっていつなのみたいな議論を電話でしたときに、「山田さんは中小企業の社長さんになりたいんですか?」と。「それだったら別に良いですけど、僕はそうじゃないと思って出資してるんで」…みたいなことを言われたときにはっと気づくわけですよ。また、だっせーな俺、そうだよな限られた時間の中で成長することが起業家の価値だよなと。そういったところを改めて言っていただいて、ふんどしを締めるじゃないですけど、覚えていますね。
和田:いやー、全然記憶にないですね(笑)。でも、考え抜いてないけど何となくそれっぽい結論を出しちゃってるなっていうときはなんとなく分かるんですよ。そういうときに、「本当にめっちゃ考え抜いて、それが絶対良いと思えているのか」を問うような質問はしますね。
ーー逆に和田さんから見て、山田さんの印象的なエピソードは。
和田:どれだろうな。このプロダクト自体がめちゃくちゃ山田さんぽいなと思います。もちろんエンジニアの方とかCSの方とかと合わせて1つのサービスですが、このプロダクトが何を目指して何を提供していくのか、従業員の方もそうですし、人事部の方、経営者の方に対して、「自信をもって関係者全員にとって良いものを追求する」みたいのは山田さんぽいなと思っていて。分かりやすいエピソードじゃないですけど、日々のそういう細かな積み重ねが事業にでているなっていうのが1つ明確にありますね、
あとは、iCAREってカルチャーとか企業文化っていうのに凄く力を入れてまして。採用もすごい丁寧にプロセス設計やオンボーディングをやっていますが、組織を作っているものも山田さんがこだわっているからこそなんだろうなって思っています。日々出てくるアウトプットにiCAREらしさ、山田さんらしさとか、主要なメンバーのみなさんの個性がすごい出てきていると思いますが、中野さんを抜擢してあれだけ自由にやってるところも、中野さんのキャラクターの素晴らしさや魅力もありつつ、山田さんのリーダーシップの形の一つなんだろうなと思っていて。ああいうこう現場の人が勢いよく引っ張ってくれていて、それがいろんなセクションで共用されてて後押しされているというのはすごい良いことだなと思いますね。
目指すは1人ひとりにスポットライトが当たっていくような組織

――組織・文化の話が出ました。iCAREの社員の皆さん、素敵な方々ばかりですよね。
山田:ありがとうございます。
和田:中野さんに食われてたりとかしてない?
山田:食われるかもしれません。営業先で「あれ?中野さんの会社ですよね」みたいなことをたまに言われてるらしくて。前よく「兄弟ですか」って言われたんだけど、似てないだろみたいな。10個も違うわ、しかも。
――今後10年、20年でどんな組織を作っていきたいか、どんな文化の会社を作っていきたいかというのはありますか?
山田:まず、事業成長というものが我々にとって何より最優先で大事なことではありますが、事業成長を通して、個人のキャリアアップやスキルアップできる場所が提供できるかということは大事にしたいです。
とはいえ、価値観や成長のスピードは人それぞれだと思うんです。ただ、みんなが気付いていないだけで、1人ひとりにiCAREに献身的になっている瞬間があるんですよ。そういう人たちこそすごい大事なんじゃないかなという気がしますね。そういうスポットライトが、1人ひとりに当たっていくようなチームにしたいです。例えば、小学校で昼休憩になると、男子が外で遊んでたり女子がお喋りしたりしている中、真っ先に黒板を消している人とかいますよね。その人が黒板消してるのはクラスのためだったり、次の先生が授業をしやすくするためです。そういう人にありがとうと言えたり、称賛できるような組織でないといけない。特にこれからどんどん大きくなっていくので、尚のことそういったことが重要になってくるフェーズになります。
週次の全体定例でも、社員から募った『サンクスメッセージ』を「○○さんありがとう」って発表します。毎回5個から10個くらいは出てくるんじゃないですかね。
ーーそこでの評価は人事にも活かされる?
山田:無意識にあるんでしょうね。「こういうところお前らしいよね」とか。でも「お前OKR達成してないのに何他の人の手助けしてるんだよ」ということもありますね(笑)。 でもそういうのも含めて、その人らしさだと思います。
あとはSlack上で、我々は「Good Job Carely」って呼んでますけども、エンジニアが作ったGJ Carelyっていうアプリを2年前くらいから運用してます。ありがとうと言いたい人に対して、Slack上でいわゆる「ありがとうバッジ」が贈られるみたいな仕組みです。それを週次で、「Giver」と「Taker」、つまり称賛をした人と受けた人をそれぞれ発表しています。そういう一つ一つがスポットライトなんです。本当に見えづらい部分ではありますが、見えづらい中でも個人のそういった動きに気付くために何が出来るかを考えて取り組んでいる施策の一環ですね。
あとはクレド・バリューの他己紹介をやっています。リレー形式になるんですけど、全体定例で、「誰々さんのクレドのこういうところがよかったです」というのを共有していく。より具体的なメッセージングなので「そういうことやってたんだ」「そういうことにプロとしての誇りを感じていたんだ」という気づきを得られるのが大きいですね。そうすると必ずその人って「えっ」ていう顔をするんです。事前に打ち合わせしてないので。嬉しいじゃないですか。部門を超えて見てくれることもあります。「誰かが見てくれている」という、iCAREの組織に対する献身的な取り組みを称賛できる場所を作っていく。
ーークレドが浸透しやすくなりますね。
そうそう。クレドは抽象的な概念になってしまうので、改めてクレドはこういう意味なんだよ、というのを伝える場になっています。例えば、「仲間に愛があるか」というクレドは、概して「優しさ」みたいに囚われやすいんですよ。同僚に対して優しいのは当たり前のことなので、そんなこと求めてないんですよね。事業の成長やお客様のためになることを追求していくと、当然意見がぶつかることがありますが、それを伝えていく中でプロとして成長していくと。その前提で愛があるか。そういった意識統一をしています。
こういう一つ一つの施策って、経営陣から提案してやっているものもあれば、現場から「こういうのやりたいです」ということもあったりして、そういう意見を融合しながら実行しては改善してを繰り返し、続けているのが上記の3つです。どれも2年以上継続してますね。
「iCARE」という名前が広まるほど、予防医療インフラがどんどん作られていくということ
――最後に、この事業を通してどんな社会にしたいか、この会社がどんなビジョンを持っているかを教えて下さい。
山田:我々iCAREっていう会社は、当時は不可能だと言われていた領域で確実に成果を出し、「働くひとと組織の健康を創る」というビジョンの元、60名を超える仲間とともに、こうやって大きな海原でしっかりと前に進めているということを非常に嬉しく思っています。

社会の中の課題にはまだまだ大きなものがありますので、これから我々ももっともっと成長して、そういった課題を一緒に解決し、日本だけじゃなくて東南アジアや世界で展開できるようなサービスにしていきたいなと思っています。これから「iCARE」という名前や「Carely」というサービスがみなさんの耳に届いていく機会が増えるほど、世の中の予防医療のインフラがどんどん作られているんだなと感じてもらえばと思っています。
同時に、iCAREという会社にに興味があるという方は是非連絡して欲しいなと思います。本日はありがとうございました。
和田:もちろん、まだ道半ばで、目指しているところから比較すると先は長いなと思ってはいるんですけど、本当に働く従業員の方々、企業の経営者や人事の方々とかゆくゆくは医療業界の方々の予防医療の分野で出来ることを増やしていきたいと思っていて、圧倒的に正しいことや世の中に必要とされること、「Carelyがあってよかったよね」と思えることを真っ直ぐに作っていって欲しいなと思っています。そういうことがどこまでやれるかはやってみないと分からないですが、最大限やってくれる会社だと思うので、医療の問題も、働く人が減っていてそんな中で長くパフォーマンスを出し続けられるかという問題も、どちらも大きな社会課題なので、そこにアプローチできる応援しがいのある会社だと思っています。
ーーありがとうございました!