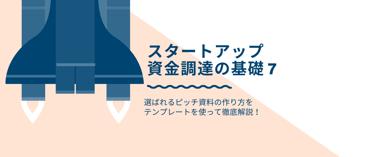グローバルで急成長を続けるAI技術。その影響を強く受けながら、日本のスタートアップエコシステムも変化を遂げています。そんな中、既存産業に特化したAI技術の活用で新たな革新を促そうとするのが、インキュベイトファンド(IF)出身の南出昌弥氏。
「既存産業×AI技術」を具体化すべく、南出氏が立ち上げたベンチャーキャピタル(VC)「ハイペリオン」は、単なる資金提供にとどまらず、スタートアップと共同創業しながら未来を共に描くというユニークなアプローチを展開しています。
南出氏が描くスタートアップ支援のビジョンや、ハイペリオンの特徴、そしてAI技術を通じた産業変革についてお話を伺いました。
◾️「伴走」を超える共同創業というアプローチで起業家を支援
— ハイペリオンはどのようなVCなのか教えていただけますか?
南出:ハイペリオンは、既存産業をAI技術を活用して変革していく創業期(プレシード期)のスタートアップ企業に投資するベンチャーキャピタルです。AI技術の社会的普及が進む中で、日本国内でAI特化型のVCはまだ少なく、そこに対してリスクマネーを提供することで、スタートアップのエコシステムを強化したいという想いから設立しました。
— 海外と比べると、日本のAI特化型VCの数はまだ少ないのですね。
南出:そうですね。日本ではまだ4社程度に留まりますが、海外ではその数十倍から100倍の規模があります。AI関連の起業家増えていく中で、資金さえあれば新しい事業に挑戦できるスタートアップ企業も多いはずです。そんな起業家たちを支援することが、私のミッションだと考えています。

— ハイペリオンのユニークなポイントは何でしょうか?
南出:大きく二つあります。一つは、投資領域を生成AIエージェントやLLM、自然言語処理、画像認識などAI全般の技術に対して注力している点です。そしてもう一つは、スタートアップを共同創業という形で支援する投資手法も取り入れている点です。具体的には、私自身が事業アイデアを考え、それを基に起業を目指す方と一緒に事業を立ち上げています。単に投資をして終わりではなく、取締役として経営に深く関わることで、スタートアップの成功に向けて共に挑戦する仕組みです。
— まさに「伴走型」を超えた関わり方ですね。
南出:そうですね。「伴走」という言葉も使いますが、私の場合はさらに踏み込んで、共同経営者として事業を一緒に作り上げていくのが特徴です。もちろん、投資先が増えてきた際には、各社に求められる役割を担いつつ、バランスを見て権限移譲や伴走型の支援に切り替える選択肢も持っていますが、共同創業というアプローチはハイペリオンならではだと思います。
現在、4社への投資が決まっているのですが (2024年11月30日時点)、そのうち1社は共同創業での投資先になります。
— すでに、共同創業という形での投資もされているのですね。既存産業×AI技術に着目した理由を教えていただけますか?
南出:日本ではここ10-15年ほどで、既存産業に対するソフトウェア・サービスの導入が進み、課題解決が図られてきました。いわゆるSaaSブームです。しかし、AIの特異点を超えた今、生成AIの技術が新たな産業構造の変革を引き起こしています。これまでの識別AIとは異なり、生成AIは「人が担わなくても良い労働集約型のタスク」から解放する可能性を持ち、産業全体に与えるインパクトが非常に大きいです。そうした背景から、既存産業におけるAI活用の可能性を模索することが重要なタイミングだと考えています。
— 特に注目している領域はありますか?
南出:規制産業には大きなチャンスがあります。ヘルスケアやフィンテックといった分野では、大企業では手が届かない部分をスタートアップがAI技術を活用して切り開ける可能性があると考えています。また、特定ドメインのBPO業務をAIエージェントを活用して高い利益率を出していくようなテーマには関心があります。

ギリシャ神話の神様の名前でもあり、世界で最も高い樹木の名前であるハイペリオンを社名に。独立したキャピタリストとして志を高く持ち、出資先と共に高みを目指していきたい、という想いを込めて命名。
◾️「人」と「事業家目線」で描く投資の未来
— 投資を行う上で、大切にされていることは何ですか?
南出:一番大切にしているのは、「この人と一緒に未来の景色を見たいかどうか」です。アイデアや技術だけでなく、創業者やチームとの信頼関係が重要であり、私がそこに関与する意味があるかどうかも考えます。特に創業期においては、事業を成立させるまでのハードシングスが多く、それを柔軟に乗り越えられるチームであるかどうかが成功を左右します。信頼出来るチームに私が加わることによって、課題解決していく未来の解像度が高まっていくことを意識しています。
— そうした価値観は、これまでのキャリアで培われたものですか?
南出:そうですね。投資銀行やIFでの経験を通じて、多様な事業や起業家に触れる中で、投資先との相性や信頼関係の大切さを強く実感しました。
— 投資銀行から転職する際、なぜIFを選ばれたのでしょうか。
南出:当時、金融業界でのスキルを活かせる転職場所として、IPO直前の企業に投資するレイターフェーズのVCが主流でした。でも、私はもっと創業期に近いところで、事業が生まれる瞬間を支援したいと考えていました。投資銀行での経験を活かして、大きなファンドで投資活動をするのも一つの道でしたが、それよりも、もっと事業に近い立場で支援できる場所を選びたかった。その点、IFは創業期に特化したVCであり、まさに自分がやりたかった仕事だと感じました。
— それが入社の決め手だったんですね。
南出:IFには独立を推奨する文化もあります。VCでの仕事は個の名前で仕事することが主流でもあります。私自身も将来的に自分でファンドを立ち上げたいという気持ちを持つだろうと思いました。独立の準備をしながら経験を積む場所として、IFが最適だと思いました。
そして、もう一つ大きな理由が、村田祐介さん(IF 代表パートナー)というキャピタリストの存在から学ぶ機会です。IFには独特の「徒弟制度」があります。村田さんは、もともとエンジニアとして学生の時に起業された後、ベンチャーキャピタリストとして活躍している方です。私が学びたいと思ったのは、事業経験のあるVCの視点でした。アメリカではエンジニアや起業家出身のベンチャーキャピタリストが多く、非常にスタンダードなスタイルです。事業を経験した人がどのようにスタートアップを支援するのかを実際に学びたくて、インキュベイトファンドに入社することを決めました。
— 事業経験があるVCのアドバイスには、起業家としても大きな説得力があると感じますよね。
南出:その通りです。特に創業期のスタートアップにとって、事業の最初の一歩をどう踏み出すかは非常に重要です。だからこそ、私は事業経験のあるVCから学びたかった。村田さんのように、事業の立ち上げから支援まで、実際に経験している人の意見がどれほど価値のあるものか、スタートアップを支援していると痛感します。

◾️AI特化型VCをさらに尖らせる未来への展望
— IFでの体験や学びをもとに、今後、ファンド、そしてジェネラルパートナーとして目指したいことを教えてください。
南出:まずはファンドのジェネラルパートナーとして、投資先を成功に導くことが目標です。成功の定義は企業ごとに異なりますが、共に描いたゴールまで必ず到達させることを大切にしたいです。またファンドとしては、AI特化型VCとしての「尖り」をどれだけ鋭くできるかを追求していきたいです。
— 南出さんの存在があることが起業家にとってはとても心強いですね。ハイペリオンを通して、今後、既存産業市場に大きなインパクトを与えることを期待しています!ありがとうございました!